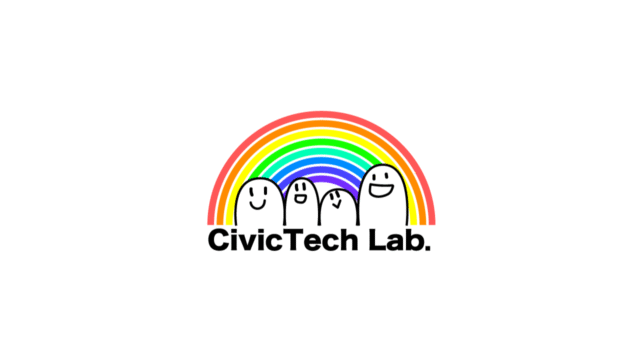実施概要
湯沢市では、新型コロナウイルス対策として全国で給付が行われた「特別定額給付金」において、市民の不安を少しでも軽減しようと、LINE上で給付受付状況を確認できるBotを導入。シビックテック・ラボとの連携により、ニーズの掘り起こしから機能の実装までを短期間で行った。サービスデザインの考え方をベースに、市民に寄り添う行政DXの好事例となった。
- 団体名:秋田県湯沢市
- サービス名:サービスデザイン研修
1.実施内容
1.実施内容
課題感・状況 ― 申請したのに、届かない。その不安を、どう減らせるか?
2020年春、新型コロナウイルスの影響で生活に不安を抱える市民に向けて
「特別定額給付金」が支給された。
しかし、申請から給付までにはどうしてもタイムラグが生まれる。
湯沢市の窓口には、「ちゃんと届くのか」「まだ処理されていないのでは?」
という電話が殺到していた。
電話対応の現場は逼迫していた。だが、その裏には、もっと根深い課題があった。
それは、「行政の処理が見えない」という市民の不安だった。
そのとき、湯沢市は“行政サービスをデザインする”という視点から
一歩を踏み出すことになる。
取り組み ―「見えない不安」を、LINEで“見える安心”に変える
市が連携したのは、全国の自治体とともにサービスデザインやDXを進める
シビックテック・ラボだった。
初回のやり取りから、ゴールは明確だった。
「市民が、給付金の申請がどうなっているか、すぐ確認できるようにしたい」
プロジェクトは、LINE Botによる受付状況確認機能の開発。
複雑な機能はつけない。余計な導線もいらない。
ただ、ユーザーがLINEで申請番号を入力すれば、現在の処理状況を即座に返す。
設計のプロセスでは、サービスデザインの手法が活かされた。
市民の困りごとは何か、その体験において、「詰まっているポイント」はどこか、
情報はどう届けると自然に“安心”に変わるのか
それらを見極め、最も自然なタッチポイントとしてのLINEを選んだ。
実装後は、現場との確認と改善を繰り返し、短期間で安定運用に移行した。
価値創造 ―「問い合わせる側」も、「応える側」も、変わった、
LINE Botの導入後、湯沢市の庁内では明らかな変化が起きた。
当初、市は市民からの問い合わせに対応するために専用のコールセンターを設置していた。
しかし、実際にはこのコールセンターの利用はほとんど発生しなかった。
代わりに、市民の多くがLINE Botを活用し、自ら申請状況を確認するようになっていたのだ。
実際、全世帯の40%以上がLINE公式アカウントを友達登録。
Botを通じて手軽に状況を確認できる手段が、市民の間に定着したことを示している。
一方で、電話がかかってきた場合でも、職員がLINEの管理画面から即座に
申請状況を検索し、回答できる体制が構築された。
Botの導入によって、市民が“問い合わせる必要がなくなる”環境が生まれただけでなく
仮に問い合わせがあったとしても、職員側がストレスなく応答できる
オペレーションが確立された。
このように、市民と職員、双方の体験を同時に改善する設計が
サービスデザインの考え方によって具体化されたのである。
結論
湯沢市がLINE Botを通じて取り組んだのは
システム導入ではなく、“市民の安心を設計する”という挑戦だった。
その根底には、サービスデザインの考え方があった。
市民の視点でサービスを見つめ直すこと。タッチポイントを慎重に選び、設計すること。
そして、必要最小限で“最大の納得”を提供すること。
それは決して派手ではない。けれど、確かな変化を生む。
これが、これからの行政サービスに求められる
サービスデザインの“第一歩”なのかもしれない。
2.デジタル × デザイン × データ
2.デジタル × デザイン × データ
※ご覧のサービスの中で、デジタル、デザイン、データがどの程度必要になるか、の指標です。
100:がっつり伴走型で実施
50:座学またはショートワーク
0:無し
4.詳しく知る
4.詳しく知る
サービスデザイン研修について
費用感や実施回数、サービスの内容を知りたい方はサービスのページをご覧ください

Let’s go & Next challenge !
どこから始めたらいいかわからない。また失敗してしまうのではないか。
そんな思いがある人、今度こそ、一緒に変えていきませんか?
自治体・企業の方はこちら