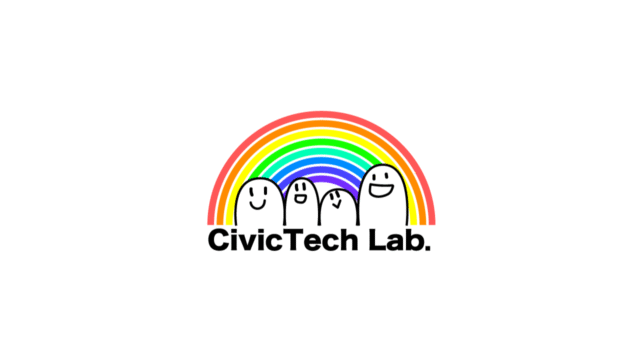実施概要
コロナ禍で生活困窮相談が急増する中、NPO法人POPOLOでは、対面・電話に代わる相談手段の必要性に直面していた。SNSで状況を知ったシビックテック・ラボが声をかけ、LINEを活用した生活相談窓口の共創がスタート。導入初期から相談件数は増加し、今では行政との連携や他団体との協働も視野に入る。NPOの支援現場に寄り添った、デジタルを活用した「支援のしくみづくり」の事例である。
- 団体名:NPO法人POPOLO/支援団体・社会福祉法人関係者
- サービス名:ICT支援
1.実施内容
1.実施内容
課題感・状況
2020年春。新型コロナウイルスの影響が拡大するなか、
NPO法人POPOLOでは想定を超える生活相談が寄せられていた。
「これまでの5倍くらいの件数が来ているんです」
Facebookでの何気ない投稿に、その異変は表れていた。
電話や対面での支援が中心だったこれまでの体制では、明らかに手が足りない。
加えて、相談者側も今までとは違う層の人たちからの連絡がきている
今までの問い合わせとは明らかに違う。
支援の必要性が高まる一方で
支援に“たどりつけない”人が増えているのではないか。
その投稿をきっかけに
シビックテック・ラボから「何かお手伝いできることはありますか?」と声をかかる。
ここから、LINEを活用した生活相談支援の共創が始まった。
取り組み
まず最初に行われたのは、相談者の「入り口」に寄り添うこと。
電話やメールでは心理的・物理的ハードルが高い人たちが
「LINEなら気軽に話せる」と感じてくれるよう
LINE公式アカウントでの“お悩み相談窓口”の立ち上げが決まった。
シビックテック・ラボは、技術的な支援だけでなく、
- 登録・投稿の導線設計
- 漫画やチラシなどわかりやすい広報支援
- 相談受付のオペレーション整理
- 対応フローの見える化(FAQ・タグ分け)
など、支援のプロセスそのものの設計に深く関わった。
「支援する人の負担が増えない」「相談者が途中で諦めない」
仕組みを意識して、LINEの応答・整理ツールを構築。
さらに、どのような相談がどれだけ届いたかを分析できるよう
ダッシュボードによるデータ集計も導入された。
LINE上には、選択式で相談カテゴリを選べる機能や
POPOLOの活動・連携先への案内も設置。
短期間で立ち上がったこの取り組みは
現場の運用に寄り添いながら改善を重ねていくアジャイルな支援として進んでいった。
価値創造
LINE窓口を開設してから数週間で、新たな層の相談者が増え始めた。
これまで支援につながらなかった若年層や、女性の利用者が目立つようになり、相談内容も多様化した。
「こんな形で相談できると思っていませんでした」
「LINEから市役所の支援につながりました」
POPOLOでは、相談の対応だけでなく、LINEで得たデータをもとに
新しい支援ニーズの傾向を行政と共有する機会も生まれている。
さらに、他のNPOや自治体でもこの取り組みに関心が寄せられ
LINE相談の汎用化や、協働による展開可能性も模索され始めている。
LINEという身近なツールを通じて
“声をあげづらい人の声”が可視化され
支援のつながり方そのものを広げているのである。
結論
NPOの現場におけるDXとは、「効率化」でも「デジタル化」でもない。
それは、支援の現場にある“声にならない声”に、新しい入り口をつくること。
POPOLOのLINE相談は、その入り口をどうつくるか
どう支えるかを、支援者とテクノロジーの力で共に考え、実装した事例だ。
共創から生まれる支援のかたちは、どの地域でも再現可能であり
今後のNPOや社会福祉法人のあり方にヒントを与えてくれるだろう。
2.類似記事
3.詳しく知る
3.詳しく知る
サービスについて詳しく知りたい
費用感や実施回数、サービスの内容を知りたい方はサービスのページをご覧ください

Let’s go & Next challenge !
どこから始めたらいいかわからない。また失敗してしまうのではないか。
そんな思いがある人、今度こそ、一緒に変えていきませんか?
自治体・企業の方はこちら