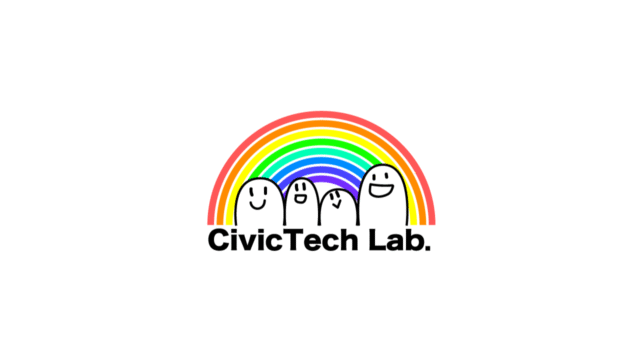実施概要
富山県黒部市では、地域の支援が重なり合い、全体像が見えづらいという福祉現場の課題に対して、複数の取り組みが動き出している。フードマーズ(WaWaWaネットワーク)ではシビックテック・ラボがファシリテーションによる場づくりを支援。福祉版MaaSでは調査・分析を通じた仕組み化、さらに社協業務のDXではデジタル化・データ連携を推進した。支援現場に寄り添いながら、継続可能な“地域福祉の見える化”が形になりつつある。
- 団体名:黒部市社会福祉協議会/地域のNPO・福祉団体/全国の福祉支援実践者
- サービス名:ICT支援
1.実施内容
1.実施内容
課題感・状況 ― 支援はある。けれど、つながっていない
「同じ人に食料支援が2回届いてしまった」
「移動が難しい方がいるけど、誰が送迎に行けるのか分からない」
富山県黒部市の福祉現場では、こうした“もったいない重なり”や
“見えない空白”が支援の課題として浮かび上がっていた。
地域の支援活動は決して止まっていない。
むしろ、コロナ禍をきっかけにNPO・ボランティア・行政・社協がフル稼働していた。
けれど、支援をつなぐ全体設計や共通の「見える地図」がないまま
各自が全力で動いている――それが現実だった。
この状況をどうにかしようと立ち上がったのが、「WaWaWaネットワーク」や
「福祉版MaaS」、そして「社協DX」といったプロジェクト群である。
取り組み ― 支援のつながりを“設計し、見える化する”プロセス
これらの取り組みには、シビックテック・ラボが中核支援者として関わっている。
単なる技術導入やDXの枠にとどまらず、場づくり・調査・業務設計・データ活用まで
一貫して支援している点が特徴だ。
フードマーズ(WaWaWaネットワーク):地域支援者が“語り合える場”をつくる
「食料支援をもっとスムーズに」という現場の声から始まったこの取り組みでは
多様な支援団体が一堂に会する対話の場を、シビックテック・ラボがファシリテートした。
進行は中立的に、けれど目的には明確に。“誰かを責める”会議ではなく
「どうすればうまく協力できるか」を見つけ出すためのプロセスデザインがなされた。
話し合いは単発では終わらず、支援内容の整理や情報共有のルール作りにつながっていった。
黒部市福祉版MaaS:移動困難者を取りこぼさない仕組みづくり
一人では通院も買い物も難しい高齢者や障がいのある方のために、送迎支援のマッチングやニーズ調査を実施。
シビックテック・ラボはここで、調査設計から集計・分析・報告までを一貫して担当し、行政や社協、交通事業者との協議の場づくりにも寄与。
「ただの移動手段の整備」ではなく、地域の支援者がどう動けるか、どう連携するかという“支援の交通整理”が進められた。
社協ヘルパーDX:日々の業務を、少しずつ効率よく
黒部市社会福祉協議会では、ヘルパーが毎日の訪問業務を紙で記録していた。
記録漏れ、確認作業の煩雑さ、情報共有のタイムラグ――こうした課題を前に
シビックテック・ラボが業務フローの可視化とデジタル移行を支援。
スマートフォンやクラウドを用いた記録・確認ツールの検討が進み
現場の声を反映しながらデータ活用の第一歩が踏み出されている。
価値創造 ― 「見える」「つながる」が、地域を支える力になる
これらのプロジェクトの共通点は、“つくって終わり”ではなく、地域の支援者たちと一緒に「つくって、育てていく」ことにある。
たとえば、LINEでの生活支援相談受付も、当初は市民や関係者の反応を見ながら機能を調整。食料支援や送迎支援も、現場の担当者が使いやすいように情報共有の仕組みを整えた。
結果として、支援の重複は減り、対応の「抜け」も減った。
何より、「自分たちのまちの支援が、全体でどう動いているか」が
関係者に見えるようになった。
結論
福祉の現場にデジタルを入れることは、IT化でもシステム化でもない。
それは、**人と人のつながりを、もっと無理なく
持続的に支えるための“仕組みづくり”**である。
黒部市の取り組みは、それをファシリテーション・調査分析・業務設計・データ活用
といった複数の角度から丁寧に進めてきた。
そして今、それぞれのプロジェクトが一つの大きな地図としてつながり始めている。
NPOや社会福祉法人にとっても、「自分たちの支援が、地域の中でどう見えるか」は
これからの連携と持続性のカギとなるだろう。
2.類似記事
3.詳しく知る
3.詳しく知る
社福/NPO向けのサービスについて詳しく知りたい
費用感や実施回数、サービスの内容を知りたい方はサービスのページをご覧ください

Let’s go & Next challenge !
どこから始めたらいいかわからない。また失敗してしまうのではないか。
そんな思いがある人、今度こそ、一緒に変えていきませんか?
自治体・企業の方はこちら