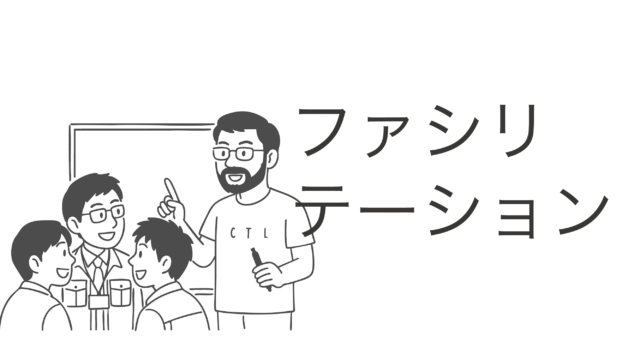実施概要
会津若松市では2019年から、公共施設マネジメントを契機に市民参加の対話づくりに着手。中立性と設計力を特徴とするシビックテック・ラボのファシリテーション支援のもと、議論を可視化するグラフィックレコーディングを活用したタウンミーティングが始まった。地域ごとに異なる設計で行われた対話は、市民の納得感と参加意欲を生み、自走する担い手も育成。今では地域全体に“考え、描き、伝える”文化が根づきつつある。
- 団体名:会津若松市/市民活動団体「みらいくる」
- サービス名:ファシリテーション研修
1.実施内容
1.実施内容
課題感 ―「話し合っているのに、進まない」
2019年、会津若松市では公共施設マネジメントの本格化に伴い
市民との対話の方法に課題を抱えていた。
市の職員たちは繰り返し話し合いを重ねていたが、議論はかみ合わず
目指すゴールにたどり着くことが難しい。市民との距離感も拭えない中
「どうすれば“話し合い”が“前進する議論”になるのか?」という問いが浮かび上がった。
当時、データ利活用研修などを通じて関わりのあった
シビックテック・ラボに相談を持ちかけたのが、最初の一歩だった。
取り組み ― 描くことで議論がつながる、新しい対話のかたち
最初の打ち合わせから、その手法は印象的だった。
シビックテック・ラボのスタッフは、議論の進行を止めることなく
その場でホワイトボードにグラフィックレコーディングを描きはじめた。
キーワードが可視化され、議論の流れが図解として浮かび上がっていく。
誰の意見が無視されることなく、会話の中に“構造”が生まれる。
この体験が、市の職員たちにとっての転換点となった。
また、ファシリテーションでは、ゴールは何か?何を目指しているのかを掘り下げる。
これが終わった時に、どのような状態に市民となるのかを問われる。
「この方法、この可視化を市民と共有したい」
「ファシリテーションとグラレコを取り入れたタウンミーティングをやってみよう」
そうして始まったのが、公共施設マネジメントに関する地域別のタウンミーティングである。
一律ではない、「地域ごとの設計」
シビックテック・ラボのファシリテーションの特徴は、「中立性」と「設計力」にある。
特定の立場に偏らず、議論の土俵を整える役割として場に臨む。
そして、目的に合わせて地域ごとにアジェンダや時間構成を調整。
たとえば高齢者の多い地区では話しやすさを重視し
住民活動が活発な地区では意見の掘り下げに時間を割いた。
いわゆる“司会”ではなく、「議論の交通整理役」として
必要なときは話を止め、また動かす。
さらに、グラフィックレコーディングも“伝えるための
ファシリテーション”の一部として活用された。
市民とともに描き、市民が担い手に変わっていく
1年にわたり、市全体でのシンポジウムと
各地域の公民館で2回ずつのタウンミーティングが実施された。
その場には、市民講座で育ったグラフィッカーや
長岡造形大学の学生も参加。
描かれた議論は壁に貼り出され、目に見える“まちの声”として会場を彩った。
最終報告会では、全地域のグラレコを一堂に展示。
違いと共通点を並べて見ることで、地域ごとの優先課題や
市全体としての方向性が、視覚的に立ち上がった。
この経験が、市民の中に「自分たちで場をつくる」意欲を生み出した。
次年度以降、ファシリテーターとグラレコ人材を育てる研修が継続され
今では地域団体「みらいくる」などが自立的にタウンミーティングを運営するようになっている。
活動は市外にも広がり、福島県内の他地域との連携も始まっている。
価値創造 ― “可視化された対話”が残したもの
タウンミーティングに参加した地域の社協職員は、後日の会議でこう振り返った。
「参加者が、“今日は楽しかった”って笑って帰っていったんです」
これは、議論が“苦しいもの”ではなく、“参加してよかったと思える体験”だった証でもある。
グラフィックで記録されることで、自分の声がちゃんと残っていると感じられる。
話し合いが構造的に整理されることで、「やりとりが前に進んでいる」という納得感が生まれる。
今では、市民・団体・行政が同じツールと言語で対話を行い
それぞれが役割を果たしながら場を動かしている。
それは、一度限りの対話ではなく、地域に根づいた“合意形成の文化”へと姿を変えつつある。
結論
ファシリテーションとは、ただ場を仕切ることではない。
目的に応じて場を設計し、対話のプロセスをデザインすること。
そして、言葉を見える化し、誰もが関われるようにすること。
会津若松市の取り組みは、それが地域の中で持続可能に育つことを示している。
はじめの一歩は、外部と共に。
その一歩が、次の地域のかたちをつくり始めている。
2.デジタル × デザイン × データ
2.デジタル × デザイン × データ
※ご覧のサービスの中で、デジタル、デザイン、データがどの程度必要になるか、の指標です。
100:がっつり伴走型で実施
50:座学またはショートワーク
0:無し
4.詳しく知る
4.詳しく知る
ファシリテーションについて詳しく知りたい
費用感や実施回数、サービスの内容を知りたい方はサービスのページをご覧ください

Let’s go & Next challenge !
どこから始めたらいいかわからない。また失敗してしまうのではないか。
そんな思いがある人、今度こそ、一緒に変えていきませんか?
自治体・企業の方はこちら