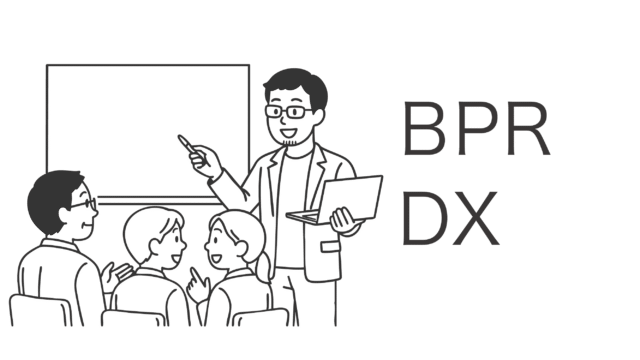実施概要
藤沢市では、自治体職員による業務改革提案を“絵に描いた餅”で終わらせないため、4つのチームに対してシビックテック・ラボと伴走型の支援を導入。プロジェクトマネジメントの技術を学びながら、要件定義・ロードマップ・予算確保へと結びつけた。照会回答、市民提案、介護申請、消防DXの4案件は検討から、実装フェーズへと進み、庁内外に着実な変化をもたらしている。
- 団体名:神奈川県藤沢市
- サービス名:BPR/DX支援
1.実施内容
1.実施内容
課題感 ―「やりたいこと」が、進まない現実
研修の中で生まれるアイデアには、確かな熱と希望があった。
「こうすれば市民の手間が減るはず」
「この業務、もっと効率的にできる」
けれどその想いは、多くの場合、紙の上で止まってしまう。
課題は明確だった。提案を“プロジェクト”として設計し
動かしきるためのスキルが職場に根づいていない。
要求定義から要件定義への深掘り。部門をまたいだ交渉。
予算化へとつなげる設計力――。そこには、伴走する誰かが必要だった。
「筋のいい種には、育てる手間をかけよう」、学びと実践が始まった。
取り組み ― プロジェクトの芽に“育て方”を
選ばれたのは、自治体変革PJ-DXから生まれた10チームのうち
可能性がもっとも高い4チーム――照会回答、市民提案、介護申請、消防DX。
それぞれに現場の強い想いがあった。
市は、シビックテック・ラボと連携し、3か月間の伴走支援プログラムを立ち上げた。
やるのは、“提案書を実装に変える”実践だ。
ステップ1|「本当にやりたいこと」を言葉にする
キックオフで確認したのは、未来の姿。
「どこまで実現したいか」「それは誰のためか」――
目的地を定めたことで、プロジェクトに“自分ごと”の火がついた。
ステップ2|プロジェクトを促進する
ワークショップでは、業務の現状と課題を可視化し、要件定義へ落とし込む。
市民提案チームは、コールセンターの刷新と連動しなければ
一元化できないという構造的課題に気づき、部門横断の交渉に乗り出した。
照会回答チームは総務課を巻き込んで、ルール変更の可能性を探り
グループウェアの更改と並走させる道を選んだ。
ステップ3|実装の設計図を描く
介護申請チームでは、アセスメント人員が増えたばかりの現場という中でも
30日以内処理の実現に向けたデジタルのポイントや要員計画を策定。
消防チームは、図面の電子化、外注の切り分け、将来的な行員廃止による
PDF配布といった段階的なDX戦略を立てた。
それぞれのチームが完成させた要件定義書とロードマップは
プロジェクトの背骨となり、翌年度以降の予算確保という現実的な足場を得た。
価値創造 ― 動き出した現場に、連鎖が起きている
2022年度以降、4つのプロジェクトは実際に動き出した。
- 照会回答は、関係部門との調整を経て問い合わせフローを刷新。
- 市民提案は、庁内で散在していた問い合わせ情報がコールセンターを起点に一元化されつつある。
- 介護申請では、変われる部分から段階的に変革させ、R6年度には目標にしていた仕組みの導入に入った。
- 消防DXでは、図面のデジタル化が始まり、電子公印の試行も見据えた設計が進行中。
こうした変化は、庁内の別の部門へも波及した。
建築指導課では、図面管理や許認可の分野でも消防DXの
スキームを応用できないかと検討が始まっている。
成果は、仕組みや紙の向こう側――「これなら自分たちもできる」と
気づいた職員たちの、確かな行動の広がりとなって現れている。
結論
プロジェクトを動かすのに必要なのは、力技ではない。
それは、正しい型を知り、実際に体験して、自分たちの言葉で進めていく力。
藤沢市が育てたのは、単なる改革案ではない。
自ら進め、仲間と巻き込み、持続可能なDXを実装する人材と文化そのものだった。
そしてこの文化は、すでに庁内のあちこちで、静かに次の種を芽吹かせている。
その種が根を張る土壌――それこそが、伴走という名の“共に進む力”なのかもしれない。
3.詳しく知る
3.詳しく知る
BPR/DXについて詳しく知りたい
費用感や実施回数、サービスの内容を知りたい方はサービスのページをご覧ください

Let’s go & Next challenge !
どこから始めたらいいかわからない。また失敗してしまうのではないか。
そんな思いがある人、今度こそ、一緒に変えていきませんか?
自治体・企業の方はこちら